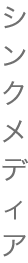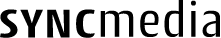シンクメディア初、無酸素でのマチュピチュ山、登頂成功のお知らせ
2016年8月半ば、僕は南米ペルーのマチュピチュ遺跡に行った。マチュピチュといえば、「空中都市」「失われたインカの都市」「映画モーターサイクルダイアリーズ」のロケ地などの異名で呼ばれ、非常に人気の観光地であるが、そこは日本のほぼ対蹠地(地球の真裏)に位置し、距離にすると約15000㎞ほど、分かりやすく東京タワーで例えると45000本分の彼方にある。しかし、現在、僕はアメリカ東海岸に住んでいることもあり、その負担は日本に住んでいた頃の約三分の一に軽減されるので、なんと東京からハワイに行くより近いのだ。この地の利を活かさない手はないと、バックパッカー時代より、予てから憧れを持っていたペルーへのチケットを手配した。

ニューアーク空港→リマ
ニュージャージー州のニューアーク空港から飛行機に乗り、ペルー共和国の首都リマにあるホルヘ・チャベス空港に降り立つ。リマはペルーの政治・経済の中心でありながら、サーフィンに適した安定した波の打ち寄せる海岸が多く存在し、サーファーの間では「世界一長い波」に乗ることのできる憧れの地である。しかし、僕は頑固なまでにフライフィッシャーである。

リマ→クスコ
リマから国内線を乗り継ぎ一時間半、クスコという高山都市に着く。この時期、南半球にあるペルーは時間帯によっては氷点下近くまで冷え込むので、冬服の準備をしていくべきだ。僕はバッゲージクレームでバックパックを受け取ると、トップリッドをこじ開け最上部に詰め込んでおいたアークテリクスのジャケットを取り出した。海抜0mのリマから、海抜3500mのクスコに到着すると、すぐさま大気中の酸素量が減少したことに気づくだろう。運動部時代に理不尽なシゴキを受けている時のような、脳内の酸素が著しく欠乏し、軽くホワイトアウトするあの懐かしい感覚がやってくる。大気中の酸素濃度が低いため、通常の呼吸数では、酸素消費量に摂取量が追いつかないので、息が乱れていなくとも、意識的に呼吸数を増やすことをお勧めする。ここで手を抜くと肉体の高度順化が旅程に間に合わず、旅の記憶は高山病の悲劇に染まることになる。

クスコ→マチュピチュ村
クスコから一時間半、ペルーレイル社の運行する鉄道に揺られ、マチュピチュ村へ向かう。列車内は中央の通路を挟み片側二席ずつ、広々としたシートが設けられている。天井まで這い上がる大きな窓は、全方位から流れ込む岩肌や空の表情、山岳地帯からアマゾンの熱帯雨林地域へと、生態系の変化する様を見逃さないための設計である。近くの山肌は落石の危うさを孕み、遠くの山肌は残雪の優雅さを帯びていた。エメラルドグリーンに湾曲する川の流れが幾度となく近づいてきては離れを繰り返し、フライフィッシャーである僕の使命感に問うているようだった。しかし、そこには降車できる駅もなく、僕には車で再び訪れる時間的猶予もない。僕は大石の陰をうかがい、流心を眺め、淀みを点検し続けた。断念を前に想像力の欠いた人間になりたくなかったし、今、この状況で示せるあらゆる誠意を以って川に接したかったからだ。「ダディー、ここで釣りできる?」「ああマイク、トラウトがいるかもしれないぞ」遠くのシートで親子が話しているのが聞こえたので、僕は顔を向け、親しみと同意の笑みを送った。

それぞれのシートには木製のテーブルが備え付けてあり、やがて乗務員により純白のクロスが敷かれると軽食と飲み物が運ばれてきた。加えて、静かに漂う伝統音楽、のんびり走り続ける列車、不足などあるまい。僕が旅行番組のナレーターであればどれほど素敵にやってのけられるだろうか。ナイフとフォークを手に、無意識のうちに口笛を吹いていることに気づくと、やはりその曲は小学生の頃に習った「コンドルは飛んで行く」であった。

マチュピチュ村→マチュピチュ遺跡
マチュピチュ村からバスに乗りマチュピチュ遺跡へ。そして翌日、マチュピチュ山も制覇する。マチュピチュ村へ着いた。温泉が湧き、坂があり、渓流が走る。その風情はまさに温泉街であり、日本人にとって馴染み深いものであった。この村からバスに乗り、待望のマチュピチュ遺跡に向かう。時々下山してくるバスとすれ違いながら急勾配、急カーブを登り続ける。決して乗り心地の良い車両ではなかったし、尻に親切な道路でもなかったが、その揺れが僕を束の間の眠りへさらい、次に目を開いた時には既に遺跡の玄関口へ到着していた。長い列に並んだ後、関所の係員にパスポートと事前に手配しておいたチケットを見せた。世界的に信用のある赤いパスポートに目をやった彼女は、つたない日本語で「コンニチハ」と微笑んだ。その人懐っこい瞳と白い歯は、僕が引きずってきた錆びた鎖のような眠気をばっさりと断ち切った。僕がマントヴァ公爵であったら、この風の中で歌を捧げ、彼女を放って置かなかっただろう。

家屋、耕作地であった場所、食料貯蔵庫であった場所、便所であった場所が次々と目の前に現れ、いつか見たことのあるマチュピチュの遠景写真とはまた異なる味わいである。かつての労働者がどのように石を切り出し、どういった順序で石を当て込んだのかを思い描き、何度となく独りよがりに頷く。眼下に滑空するコンドルがいる。ここはずっと昔から空中都市であった。空中都市の在り方、空中都市で在り続けること、空中都市で在るということはどういうものなのかを、世界中の人々にきっちりと理解させること、そこまでがマチュピチュ遺跡の運命であるかのように思えた。

マチュピチュ遺跡を囲むようにワイナピチュ山とマチュピチュ山が屹立する。双方とも一日の入山人数に制限が設けられており、数週間前から予約をする必要があるが、マチュピチュ遺跡全景を見下ろすために是非挑戦したい。

昨日と同じように長い列を経てマチュピチュ遺跡に入ると、僕は新宿地下街を歩く税理士のように、計算高く群衆をすり抜け入山口に向かった。急いだせいもあり所々足元が滑ったので「もう少しマシな靴を持って来れば良かったな」と少し後悔した。爽やかな風が僕の傷んだ長髪を撫でる。門には一人の係員がいて台帳に名前や入山時刻を書かされた。ついに立った入山口の先には静寂と樹林が織りなす暗がりが横たわっていた。人影はめっきり減り、すぐに道の傾斜は厳格な態度になるので、まるでトップガンに選抜された時のような優越感と緊張感がこみ上げてきた。僕はこの日、マーベリックが使っていたティアドロップ式のサングラスではなく、偏光レンズを備えたウェイファーラーを着用していたが、既にその頃には大粒の涙のような汗が頬を伝っていた。
時折、視界の開ける谷側を覗くと遺跡が小さく、雲が低く見えた。山道はさらに細く険しくなってきて、下山者とすれ違う時は、どちらかが片一方に寄り、道を譲り合う必要があった。道理で少し前に起きたセルフィー青年の転落事故にも合点がいく。深く呼吸をしながら顔を上げると30mほど前方で、岩に腰を掛けて休憩している女性が見えた。「やあ」と声を投げた。ブロンドの髪は短く刈られ、ダークグレーのタンクトップから焼けた肩が覗いている。装備を見るところ、かなり熟練したハイカーに思えた。彼女に追いついたところで、僕はジャケットのピットジッパーを全開にし、ペットボトルの水を口に運んだ。「コカの葉、欲しい?」上気した頬で彼女は言う。瞳は空を映したように青く、真っ直ぐに僕を見つめていた。張りのある筋肉と女性特有の弛みが不注意に彼女の輪郭を縁取っていた。その体躯はアンデス山脈と見誤り、登頂しかねない豊かな起伏を備えていることに気づいた。「悪くないね」僕は返した。


見渡すと大分高いところまでやってきたようだ。風は高木に邪魔されることなく自由に岩肌を這い、ピンクや紫のランを揺らした。下山してくる先行者が口を揃えて「もうすぐそこさ」と言う。「人は騙され続けることで擦れてゆくのだな」と一人呟いた。トラウトも偽の餌で騙され続けることで次第に擦れていくことをフライフィッシャーである僕は知っている。「そうさ、普段の行いさ」声を漏らした。僕はどこまでも受動と能動の具現者であり、体を張って両側面を学ぶ尊い研究生なのだ。見上げると混じり気なく青い空がすぐそこに迫り、目指す稜線にもはや手が届きそうだった。猫の額ほどの砂利道を踏み外さぬよう歩き、肩幅ほどの切通しを注意深く踏み超え、あるいは欧米人用に設計された無茶な階段を上がり、とうとう僕はやってきたのだ。
マチュピチュ山3061mの登頂に成功した。

頂に立つ人々は一様に疲労しているはずだったが、その顔は達成感に溢れ、声は艶を帯び、肉体からは生気がほとばしっていた。時間と金を使ったにもかかわらず、フライフィッシャーは釣った魚を逃す。登山家は登った山を下りる。ゴルファーは打ったボールを追いかける。ランナーはただひたすら走る。酒飲みは、酒を飲み、記憶すらなくす。コレクターは集めるだけ集め、ただひたすら愛でる。これらにいったいどんな意味があるのだろうか。
西日はインカの山々に影を作り始め、清々しい山風は僕たちの勇姿に似た雄叫びを遺跡に吹き下ろしていた。

淵に座るコカの娘の背中が見えた。ノートに何やら書き綴っている。遠くで待つ誰かを想いながら目を細めているのだろう。
彼女に歩み寄り「やあ、バディー。君のおかげで楽しい登山ができたよ」と伝えた。
マチュピチュ遺跡を眺めるのであれば、ワイナピチュ山かマチュピチュ山に登るべきである。
いずれも入場制限があるが、穴場は競争の少ないマチュピチュ山だ。