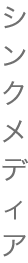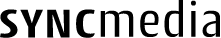ヴィタリック・ブテリンとイーサリアム:理想と現実の狭間で進化する「無限の庭」の物語
up to date : 2025.08.29 Fri

こんにちは。今日は、ドキュメンタリー映画「Vitalik: An Ethereum Story」を鑑賞したので、その概要と感想文をお届けします。この作品は、イーサリアムの創設者であるヴィタリック・ブテリンの人生と、彼が築き上げたブロックチェーン・プラットフォームの軌跡を追っています。単なる技術の話ではなく、理想主義、コミュニティのダイナミクス、そして現実の厳しさとの葛藤が織りなす人間ドラマです。ドキュメンタリーの記録から浮かび上がる彼のユニークな人物像、革新的なアイデアの誕生、そして数々の試練を通じて進化するイーサリアムの姿を探っていきましょう。技術の未来を考える上で、きっと多くの示唆を与えてくれるはずです。
ヴィタリック・ブテリン:風変わりで人間味あふれる人物
まず、ヴィタリック・ブテリンを知る上で欠かせないのは、彼のユニークなパーソナリティです。ドキュメンタリーでは、ステージに上がる前に「お茶入れてマイティ(mighty)」というダジャレを飛ばすようなユーモアあふれる姿が描かれています。彼はバックパック一つで世界中を旅するノマド生活を送り、中身は健康志向のナッツバーや100%カカオのチョコレート。ミニマリスト的なライフスタイルは、彼の価値観を反映しているようです。本人曰く、「なぜ人々は僕の話を聞くんだろう。ただのオタクなのに」と感じるほど、謙虚で内省的。物理的な拠点を持たない代わりに、Reddit、X、Telegramなどのオンラインコミュニティを「故郷」のように思っているというデジタルネイティブぶりが印象的です。幼少期のエピソードも興味深いものがあります。ロシアからカナダに移住した後、7歳で古いコンピューターのExcelに夢中になり、架空のウサギの世界を詳細に設定した「ウサギの百科事典」を作成。魔法の砂糖の成分を「魔法70%、岩15%、金属…」と細かく設定し、合計100%になるかを計算させたという逸話は、微笑ましい一方で、彼の分析的な思考の片鱗を示しています。当初はコミュニケーションが苦手だったようですが、複雑なシステムを構築する才能は早くから発揮されていました。この特性が、後にイーサリアムを生み出す基盤となったのです。

ビットコインとの出会いとイーサリアムの着想
ヴィタリックの暗号資産への関わりは、高校生時代にビットコインと出会ったところから始まります。ビットコインの技術だけでなく、経済的・政治的な可能性に強く惹かれ、ビットコインマガジンを共同設立したり、スペインのアナキスト共同体で生活したりと、既存システムの外で新しい社会を築くサイバーパンク的思想に共鳴していました。ビットコインは、既存の金融システムから排除された人々に手段を提供する革新的な技術だと彼は語っています。しかし、ビットコインの基盤であるブロックチェーンが通貨システムにとどまらないポテンシャルを持つことに気づいたのが、イーサリアムの出発点です。ドキュメンタリーでは、植物が空気と水から光合成するプロセスを例に挙げ、イーサリアムを「無限の庭」として描いています。つまり、中央集権的な仲介者(企業や銀行)を必要とせず、誰もが自由にアプリケーションを構築できるデジタルインフラ。個人同士が信頼に基づいて直接やり取りできる「世界のコンピューター」を目指したのです。この野心的なビジョンをホワイトペーパーにまとめ、知人15人に送ったところ、予想外の反響があり、共同創設者たちを集めました。「いい人そうだったし、手伝いたいと言ってくれたから」という純粋な理由でチームを組んだ点は、彼のナイーブさを物語っています。

創設の試練:理想と現実の対立
プロジェクトの初期段階で、大きな壁が立ちはだかりました。営利企業として資金を集めてスピーディに開発を進めるべきか、非営利の財団として公共的なプラットフォームを目指すか——この対立です。一部からは「クリプト版Google」のような中央集権的な成功を求める声も上がりましたが、ヴィタリックは営利アプローチに「汚い感じがした」と抵抗。公共資金が一部の株主の利益になることに違和感を覚え、最終的に一部のメンバーと決別する決断を下しました。この経験は、彼に「誰もが同じ理想のためにいるわけではない」という厳しい現実を教えたそうです。非営利の道を選んだことで、イーサリアムはコミュニティ主導の分散型プラットフォームとして信頼を築きました。2015年にローンチされ(今年は誕生10周年アニバーサリーでした!)、「ついにイーサリアムは実際に存在する。オフスイッチはない」というヴィタリックの言葉には、親のような思いが込められています。ローンチ後、イーサリアムは急速に成長し、何十万もの人々が関わるプロジェクトが生まれました。身分証明、投票システム、デジタルパスポートなどの応用が期待され、人類の協調の進化として語られるほどでした。
成長の影:NFTブームと環境問題
しかし、成長の裏側で課題も現れました。まず、NFT(非代替性トークン)のブームです。アートやコレクティブルの分野で爆発的な人気を博し、Bored ApesやPudgy Penguinsのような高額取引が相次ぎました。ヴィタリックはこの状況を「両刃の剣」と呼び、「金銭的インセンティブは火のようなもの。暖を取ることもできるけど家を燃やすこともできる」と表現。価格ばかりが注目される状況や、無断で作られた「weirdvitalik.com」などのNFTを公然と批判しました。技術の本質から逸脱していると感じたのでしょう。
次に、環境負荷の問題です。初期のProof-of-Work(PoW)仕組みは、アルゼンチン一国分に匹敵する電力を消費し、持続可能性が批判されました。これを解決したのが、2022年9月の大型アップデート「The Merge」です。Proof-of-Stake(PoS)への移行で、エネルギー消費を99.9%以上削減。「飛行中の飛行機のエンジンを交換するようなもの」と表現されるほどリスクが高かったですが、成功により全世界の電力消費を0.2%削減したとされ、環境問題への大きな貢献となりました。メディアの反応は多様で、ニューヨーク・タイムズは環境面を強調、Business Insiderは価格影響を中心に報じました。

社会的な課題と「クリプトの冬」
イーサリアムの影響力拡大に伴い、不正利用の問題も深刻化しました。FBIなどの機関が懸念するように、北朝鮮などの国家や犯罪組織が制裁回避やマネーロンダリングに悪用。匿名性と国境を超えた送金の利便性が裏目に出たのです。ヴィタリックはこれを、アインシュタインと核兵器の関係に例え、技術の中立性を認めつつ、影響を考え続ける必要性を語っています。さらに、2021年のピークから2.2兆ドルの時価総額が失われた「クリプトの冬」が訪れました。多くのプロジェクトが頓挫し、懐疑論が噴出しましたが、ヴィタリックは冷静でした。「過剰な投機が覚めて、本当に価値のあるものが残る機会」と捉えています。
この時期を通じて、彼の役割は変化します。リーダーになるつもりはなかったが、思想的な影響力でコミュニティを導く「インスティゲーター(先導者)」として位置づけています。ウクライナ戦争では、ロシア出身ながら侵攻を批判し、暗号資産を通じた支援を呼びかけ、社会的責任を強く意識するようになりました。

現在と未来:実用性への焦点
今、ヴィタリックが注力するのは投機ではなく、イーサリアムの真のユーティリティです。分散型ソーシャルメディアや、プライバシーを保護した本人確認プロジェクト(Zupassなど)に期待を寄せ、「最大の恐怖は強気相場」とまで語っています。コミュニティへのメッセージは「Keep calm and keep building(冷静に構築し続けよう)」。彼は、イーサリアムが自分抜きで自立的に発展することを望んでいます。
まとめ:理想の庭が教えてくれること
ウサギの百科事典に夢中だった少年が、世界を変えるプラットフォームの先導者へ——ヴィタリックとイーサリアムの物語は、理想と現実の狭間で進化するヒューマンドラマです。分散型コミュニティが投機、規制、人間関係の圧力に耐えながら自己変革を遂げる姿は、テクノロジーの未来だけでなく、新しい経済・組織のあり方を考えるケーススタディーとして価値があります。
最後に、ドキュメンタリーの問いを皆さんに投げかけます:技術が創設者の想像を超えて使われ始めた時、当初の意図はどれほどの重みを持つのでしょうか?この物語を通じて、そんな思いを巡らせてみてください。この記事が、皆さんの探求のきっかけになれば幸いです。
Yoshikazu Tsugiyama
category : column | posted by : Yoshikazu Tsugiyama